受動喫煙の防止について
なくそう!望まない受動喫煙「マナーからルールへ」
タバコを吸う人も吸わない人も”ルール”(改定健康増進法)を理解し、望まない受動喫煙をなくしましょう。
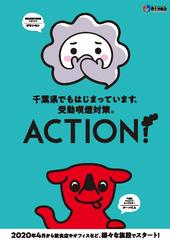
受動喫煙とは
タバコの煙には、喫煙者が直接吸い込む「主流煙」のほか、火のついたタバコの先から立ち上がる「副流煙」と喫煙者が吐き出す「呼出煙」があります。この副流煙と呼出煙を、自分の意志とは関係なく吸い込む(他人のタバコの煙を吸わされる)ことを受動喫煙といいます。
タバコの煙には、発がん物質等の有害な化学物質が多く含まれています。主流煙よりも副流煙の方に高い濃度の有害物質が含まれており、喫煙者だけでなく、周囲の人の健康にも悪影響を及ぼします。
受動喫煙にさらされていると、がんや虚血性心疾患、呼吸器疾患などの様々な病気のリスクが高くなります。
子どもへの害も深刻で、乳幼児の場合、乳幼児突然死症候群の発生率が上昇したり、気管支炎や喘息などの呼吸器疾患にかかりやすくなることが明らかになっています。
改正健康増進法
基本的な考え方
1 「望まない受動喫煙」をなくす
受動喫煙が他人に与える健康影響と、喫煙者が一定程度いる状況を踏まえ、屋内において受動喫煙にさらされることを望まない方が、そのような状況に置かれることのないようにすることを基本に「望まない受動喫煙」をなくす。
2 受動喫煙による健康影響が大きい子どもや患者さん等に特に配慮
主に子どもなど20歳未満の方や患者さんなどが利用する施設(学校や病院)や屋外について、受動喫煙対策を一層徹底する。
3 施設の種類・場所ごとに対策を実施
「望まない受動喫煙」をなくすという観点から、施設の類型・場所ごとに、主たる利用者の違いや受動喫煙が他人に与える健康影響の程度に応じ、禁煙措置や喫煙場所の特定を行うとともに、掲示の義務付けなどの対策を行う。
受動喫煙を生じさせないための配慮義務
改定健康増進法では、喫煙場所だけではなく、それ以外の場所(路上、居住場所等)を含めて、喫煙する際には望まない受動喫煙を生じさせないよう、喫煙場所を設置する際には、それぞれの配慮を義務付けています。
喫煙者、施設管理権原者、管理者の皆様には、以下のような配慮をお願いします。
- 喫煙をする際には、できるだけ周囲に人がいない場所で喫煙するように配慮する。
- 子どもや患者さん等の、特に配慮が必要な方が集まる場所や近くにいる場所などでは、特に喫煙を控える。
- 喫煙場所を設ける場合には、施設の出入り口付近や通り道、利用者が多く集まるような場所には設置しない。
- 喫煙室を設ける場合には、タバコの煙の排出先について、周囲の状況を勘案して受動喫煙を生じさせない場所とする。










更新日:2024年03月29日