令和4年度からの個人住民税の改正について
1.住宅ローン控除制度の特例期間の改正
住宅ローン控除制度の控除期間を13年間とする特例が延長されました。令和4年12月31日までの入居者が対象ととなります。ただし、注文住宅は令和2年10月から令和3年9月末までに契約したものとなり、分譲住宅などは令和2年12月から令和3年11月末までに契約したものとなります。さらに、所得金額が1000万円以下の人には床面積要件が緩和されました。床面積が40立方メートル以上50立方メートル未満である住宅も対象になります。これらの特例が適用されるのは、住宅の対価または費用の額に含まれる消費税の税率が10%の場合に限ります。
(注意)所得税額から控除しきれない額が、これまでと同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。
控除限度額は所得税の課税総所得金額等の7%(最高136,500円)となります。
2.セルフメディケーション税制の延長
対象医薬品の範囲の見直しを行った上で、その適用期間が5年間延長されました。(令和8年12月31日まで)
【参考】セルフメディケーション税制とは
健康の保持増進及び疾病の予防として一定の取り組みを行っている人が、平成29年1月1日以降に、いわゆるスイッチOTC薬の購入費用を年間12,000円を超えるときには、その購入費用のうち12,000円を超える額について、その年分の総所得金額から控除できる制度です。
3.上場株式等の配当等について所得税と住民税で異なる課税方式を選択する場合の申告手続きの拡充
上場株式等の配当等にかかわる所得金額について、所得税の確定申告を行い、住民税では特別徴収で済ませること(申告不要)も可能です。この選択をするには、今まで別途、住民税の申告が必要でしたが、令和3年分からは、確定申告書第二表の下部にある住民税関する事項「特定配当等の全部の申告不要」欄に○(丸)印を記入すると適用されるように申告手続きが簡略化されました。
4.国や地方自治体の実施する子育てに関する助成等の非課税措置
子育て支援の観点から、保育を主とする国や自治体からの子育てに関する施設・サービスの利用料に対する助成等について令和4年度から非課税所得となります。
非課税となる助成
- ベビーシッターの利用料に対する助成
- 認可外保育施設等の利用料に対する助成
- 一時預かり・病児保育などの子を預ける施設の利用料に対する助成
5.退職所得課税の適正化
法人役員等以外の勤続年数5年以下の人退職手当等については、退職所得控除額を控除した残額の300万円を超える部分について、2分の1とする措置を適用しないこととします。
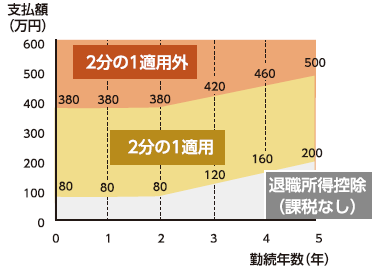
(図は、財務省ホームページより引用)










更新日:2024年12月17日